地下五百階の住人たち――最後の呪縛を通り抜けた場所 

第一章
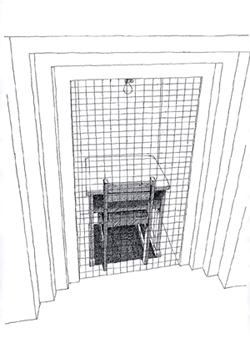 その近代的な街の中にも不思議な場所は幾つか在った。あの極限的なオレンジ色の円筒暗喩の隠れ潜んでいた地下倉庫だけではない。たとえば、暗い掲示板室に至る通路とか、大僧院の崇拝の対象となる区画とか、また、そのほか常に回想に絡み付いてきた胎内的部屋とか、数え上げれば果てしないほどに在る。だが、私は、それらの視覚で捉えることのできる空間とはまた別に、この世界にはあり得ないような霊媒的なある場所を今、空想している(空想と言えどもまさにそこにありありと居る証拠として、私は目覚めたあとにもはっきりとその細部を意識することができる。もちろん輝かしい太陽の光を浴びてのことだけど)。そこには、件の美術館の外壁に眠る阿羅漢の砂時計と同じほどの重みを持った確実なメタファーが展開されてはいた。人々が過剰な憧れを持ってその方角に走るのであろうメタファー。それは、ついに、水晶珠に結実したり、空を飛び地下を巡る未来の乗り物に異化するのだろうけれど。日常の営みを牧歌的に過ごしている平穏な商業的家庭の、何気なく開けられた地下室への扉を引き、その下方に続く長い階段を何時間も掛けて降り、もう赤い溶岩が溢れてきそうな地点まで達すると、そこに、今までも同じように普段の生活を紡いでいたような、極めてありふれた、穏和で優美な一家族が居た。その団欒の部屋の中に入り、指し示す通りにその部屋の奥に下がる簡易エレベーターに乗ると、眼下に打ち寄せる浜辺が展開され、件のエレベーターがその青い海面付近まで降下すると、そこには、地上の海辺では決して見ることのできない紫紺の真珠が、穏やかに寄せる波に揺れ、打ち上げられていた。 その近代的な街の中にも不思議な場所は幾つか在った。あの極限的なオレンジ色の円筒暗喩の隠れ潜んでいた地下倉庫だけではない。たとえば、暗い掲示板室に至る通路とか、大僧院の崇拝の対象となる区画とか、また、そのほか常に回想に絡み付いてきた胎内的部屋とか、数え上げれば果てしないほどに在る。だが、私は、それらの視覚で捉えることのできる空間とはまた別に、この世界にはあり得ないような霊媒的なある場所を今、空想している(空想と言えどもまさにそこにありありと居る証拠として、私は目覚めたあとにもはっきりとその細部を意識することができる。もちろん輝かしい太陽の光を浴びてのことだけど)。そこには、件の美術館の外壁に眠る阿羅漢の砂時計と同じほどの重みを持った確実なメタファーが展開されてはいた。人々が過剰な憧れを持ってその方角に走るのであろうメタファー。それは、ついに、水晶珠に結実したり、空を飛び地下を巡る未来の乗り物に異化するのだろうけれど。日常の営みを牧歌的に過ごしている平穏な商業的家庭の、何気なく開けられた地下室への扉を引き、その下方に続く長い階段を何時間も掛けて降り、もう赤い溶岩が溢れてきそうな地点まで達すると、そこに、今までも同じように普段の生活を紡いでいたような、極めてありふれた、穏和で優美な一家族が居た。その団欒の部屋の中に入り、指し示す通りにその部屋の奥に下がる簡易エレベーターに乗ると、眼下に打ち寄せる浜辺が展開され、件のエレベーターがその青い海面付近まで降下すると、そこには、地上の海辺では決して見ることのできない紫紺の真珠が、穏やかに寄せる波に揺れ、打ち上げられていた。
|
 |
|
|



