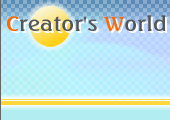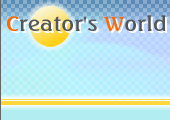|
 |




|
 |
第一回
ゼロからひとつの世界を作り上げる作家の仕事。
ゼロが1になる瞬間ともいえる、一文字目を書き付けるその時に至るまで、
プロは何を考え、何をしているのか。プロの創作の秘密に迫るインタビュー、
今回は「川べりの道」でデビューして以来、読む者の心に強く響く、
質の高い小説を発表し続ける作家・鷺沢萠さんにご登場いただいた。
第一回では“小説を書くまで”についてうかがう。

|
 |
 |
 鷺沢萠さんの作家デビューは早い。1987年、なんと18歳という若さで「文學界」の新人賞を受賞。デビュー作「川べりの道」執筆当時は高校3年生。受賞の報せは大学の入学式の直前に聞いたという。
鷺沢萠さんの作家デビューは早い。1987年、なんと18歳という若さで「文學界」の新人賞を受賞。デビュー作「川べりの道」執筆当時は高校3年生。受賞の報せは大学の入学式の直前に聞いたという。

鷺沢:
非常に「職業」ということに敏感な高校生でしたね。だけどそこは所詮高校生ですから、ガキなわけです。どれくらいガキだったかというと、大学に入れば、それなりの「職業」ってセットになって付いてくるものだと思っていた。大学は推薦で入ったんですが、ウチの大学(上智大学)は推薦で全国から集めた高校生相手に、もう一回試験やりやがるんです(笑)。踏絵だね、キリスト教だけに。って、それは冗談ですけど、つまり、学校の中で推薦を取れても、大学側が踏絵みたいな試験をきっちりと用意してて、それをクリアしないと「合格」ということにはならない。やべえよなあ。これで落ちてたら、ボクちゃんどうやって食べていくのかなあ、と。デビュー作を雑誌の新人賞に送ったのは、というか送りつけたのは(笑)、タイミングとしては試験を受けた直後くらいでした。保険、というとことばは悪いですけど、そういう感覚は確実にあったと思いますよね、今から思えば。私にとっては「どっちか」が「合格」しないとヤバいわけ。

そんな鷺沢さんは、高校3年の秋に、大学から合格の通知をもらう。

鷺沢:
オッケー! ゲット! と思いました。ガキですねえ。大学入学したくらいのことで、人生のキップもらった、みたいに思ってた。で、そっちのほうのキップをゲットしてたもんだから、雑誌の新人賞に小説送りつけたことをすっかり忘れるわけです。そのころ、週刊文春という雑誌で糸井重里さんがコピー塾っていうのをやってらして、よくネタを送ってたんですよ。親に「ブンゲイシュンジュウから電話があった」って言われたとき、てっきりそのコピー塾のほうでなんかもらったんだあ〜、と思ってました。電話で「最終候補に残ってます」って言われたときも、なんか、実感なかったですね。ふつうはその「最終候補に残った」という段階でなにがしかの感慨をおぼえるらしいんですけど、なんせガキですから。え? 候補なんでしょ? 受賞じゃないんでしょ? なんでわざわざ電話くれんの? って、純粋に不思議がってた気がする。

ところが、これが受賞してしまう。デビュー作「川べりの道」は40枚ほどの短編で、18歳の女子高生が書いたとは思えない渋い小説である。女性、しかも少女と呼んでも差し支えのない年齢の女性が男性を主人公にしたことも、話題となった。

鷺沢:
いぶし銀なの(笑)。18歳でいぶし銀なの。ラッキーだよね。自分では意識してなかったけど、18歳でいぶし銀、というあたりが、やっぱり受賞のヒミツのカギを握っている、とは思う、客観的に(笑)。

18歳の少女は、なぜ「いぶし銀」のような小説を書きたい、と考えたのだろうか。

鷺沢:
正直いって、自分でもホントに判らない。それがいぶし銀、という評価を得るだろう、ということも判ってなかったし。ただね、私、家の事情があって、80年代のバブリーな日本でかなり経済的に苦しい高校生活を送っていたんですよ。経済的に苦しい、っていうのは、当時の日本ではたいへんに恥ずかしいことだったんですね。恥ずかしいから、言えないの。私、けっこう苦しいです、っていうことを。そういうふうに、「言えない」ことが、溜まって溜まって、そりゃあもう悪臭を放つくらいに溜まりまくっていてね。身体の中で。辛いわけですよ、身体の中に悪臭を放つような何かを抱えて暮らしていくのは。それを、「書く」という形で発散させてやった、という部分はあったでしょうね。

18歳の少女が「身体の中に溜まった何か」を「書く」という形で発散させることを思いついたのはなぜか。

鷺沢:
ビンボーだからね。ミもフタもない言い方だけど。おカネが、たくさんじゃなくてもいいから、それなりのおカネがあれば、たとえば音楽に向かう、という方向性もあったと思うんですよ。だけど、音楽とかってやっぱりおカネかかるじゃない? ビンボーな場合、自己表現の方法に「書く」という手段を選ぶのは、もう必然だと私は思う。だって廉価だもの、道具が。そのころはたいていの人が手書きで書いてたし。ありとあらゆるものをね。私も、コンビニで売ってるような原稿用紙と、百円のシャーペンで書いたよ、デビュー作。

その「百円のシャーペン」を、鷺沢さんは今でも大事にしているという。

鷺沢:
私にとっては「戦友」なのね、そのシャーペンが(笑)。さすがに今は私も手では書いてないけど、一生大事にするだろうね。棺桶に入れてくれ、って遺言残しとこう。わびしい話だよね、棺桶にシャーペンを、って。それどうなんだろう、って言ってから自分でしみじみと思いました。

次回は、コンビニで売っている原稿用紙と、百円のシャープペンシルで最初の闘いに臨んだ18歳の「それから」を訊く。  |
 |
 |
鷺沢さんの「戦友」である「百円のシャーペン」と創作ノート |
|
 |