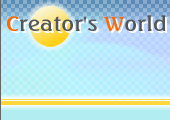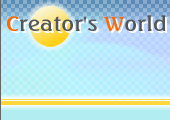|
 |
 |




|
 |
第一回
ゼロからひとつの世界を作り上げる作家の仕事。
ゼロが1になる瞬間ともいえる、一文字目を書き付けるその時に至るまで、
プロは何を考え、何をしているのか。プロの創作の秘密に迫るインタビュー、
今回は『空中庭園』でさらなる新境地を拓いた注目の作家・角田光代さんにご登場いただいた。
第一回では、“小説を書くまで”についてうかがう。

|
 |
 |
 直木賞候補にもなった話題作『空中庭園』により、いっそうの注目を集める角田光代さん。23歳の時に『幸福な遊戯』でデビューして以来、飾ることのない若者のリアルな生態や心情を巧みに描いてきた。作家を志望したのは、なんと小学校1年生の時だという。
直木賞候補にもなった話題作『空中庭園』により、いっそうの注目を集める角田光代さん。23歳の時に『幸福な遊戯』でデビューして以来、飾ることのない若者のリアルな生態や心情を巧みに描いてきた。作家を志望したのは、なんと小学校1年生の時だという。

角田:
小学校1年生の時の作文に、作家になるって書いたんですよ。それがすごく記憶に残っていて。松谷みよ子さんのモモちゃんのシリーズとか大好きだったんですけど、ちっちゃいから、本読んですごく面白いと思ったら、もうこういう仕事しかない、って思ってしまったんですね。他にどういう仕事があるか考えもしなかったんです。

その頃、彼女は膨大な量の作文を書いていたという。

角田:
小学校3年生ぐらいまで、しゃべるのがすごい苦手で、書くのが好きだったんで、たくさん作文を書いたんですよ。でも、そうすると、書くネタってなくなってくるわけです。家で起きた全てのことと学校で起きたすべてのことを全部書いてもまだ書き足りないんですよ。だから、見た夢の話を書いて、読んだ本の感想を書いたんですけど、それでも、まだ書き足りなくて、作り話を書いてましたね。ストーリーじゃなくて、でたらめ、ウソですよね。背のない国っていうみんな影みたいに移動している人たちの話なんかを書いていましたね。その世界の質感は覚えてるんですけど、それを夢で見たのか想像なのか自分でもよく分からない(笑)。それから、実際にないのに、こういう人がうちに来た、とかっていうことも書いてましたね。一歩間違えば虚言癖になりますよね(笑)。

生まれついての才能に加え、この小さい頃からの大量の書くという行為にもよるのだろう、角田さんの文章は心地よいリズムを備えていて、淀みがない。あまりにつるつると自然に書かれているので、文章を書くことの苦労がそうないのではないかと思ってしまうほどだ。

角田:
あ、でもね、慣れてるは慣れてるんですよね。口で言うより書く方が全然早いんですよ(笑)。だから、言葉が出てこないとか、これを書きたいのに書けないとか、実はないかもしれない。

意外なことに大学生になるまで、小説というものを書いたことはなかったのだという。

角田:
作文はとにかくすごくいっぱい書いたんですけど、小説だけは書けなかったですね。書き方がそもそも分からなかったんです。私が二十歳ぐらいまで、同世代の作家がほとんどいなくて、当時共感できる小説の書き手といったら太宰治ぐらいしかいなかったんです。雰囲気を味わうとか、この感じ!っていうのを読むとかってあり得なかったと思うんですね。身近な言葉で語った小説っていうのがなかったから、どうやったら書けるんだろうなっていうのをずっと思っていましたね。それで大学に入って、小説を書く授業がある文芸科に行ったんですが、そこの課題として書いた小説が最初です。

宮沢賢治、太宰治、梶井基次郎など、様々な作家の本を片っ端から読んでいた角田さんだが、直接の書くきっかけとなった小説は、同世代の学生が書いた小説だった。

角田:
大学で、『蒼生』という文芸科の機関誌をもらったり、授業で上の学年の小説を紹介してもらったりしたんですね。それが、ものすごく、「え! それでいいの?!」っていう小説だったんですよ。すごく身近な題材を身近な言葉で書いた短い話で。それでいいんだったら、じゃあ、書ける!って思って課題に積極的に取り組みましたね。最初に書いたのは、手っ取り早く言えば失恋小説です。文芸科の授業が始まるのは二年生からなんですが、その最初の課題が出た時に、ふられかけていたので、その話を下敷きにちょっとストーリー風にして書きました。

小説家になる以外の道をまったく考えていなかった角田さんは、大学に進む前から、就職活動をするつもりはなかったのだという。

角田:
そこにいけばなんか作家への道があるだろうと思って文芸科に行ったんです。就職活動っていう考えがそもそもなくって、大学自体を就職斡旋所みたいな風に捉えてましたね。文芸科は、だから、私にとっては職業安定所みたいなイメージでした(笑)。

そして、角田さんは大学在学中に少女小説作家となり、早くもプロの作家としての道を歩み始める。
 |
 |
 |
 |




|
 |
第三回
ゼロからひとつの世界を作り上げる作家の仕事。
ゼロが1になる瞬間ともいえる、一文字目を書き付けるその時に至るまで、
プロは何を考え、何をしているのか。
プロの創作の秘密に迫るインタビュー、
今回は『空中庭園』でさらなる新境地を拓いた注目の作家・角田光代さんにご登場いただいた。
第三回では、その“「空中庭園」ができるまで”についてうかがう。 
|
 |
 |
 「エコノミカル・パレス」の後に発表された「空中庭園」は、一見平凡な家族の秘密や思いがそれぞれの視点から語られる、角田さんの新境地とも言える連作短編集だ。
「エコノミカル・パレス」の後に発表された「空中庭園」は、一見平凡な家族の秘密や思いがそれぞれの視点から語られる、角田さんの新境地とも言える連作短編集だ。

角田:
35歳になって、フリーターとか、本当にやりたいことは別にあるんだって言ってられる年齢じゃないって気づいちゃって。「幸福な遊戯」以来、ずっとフリーターを書いてきて一巡しちゃったんですよね。これ以上フリーターを書いていても、多分同じ所をぐるぐる回るだけって気づいたんです。「エコノミカル・パレス」以前ってある意味、私小説というか、私を取り巻く物語なんですね。それが私の視点ではないものを書かないと自分自身も興味がもう持てなくなってきたんですね。それまでってわりと私中心だから、“私”と“見えるもの”ってふたつで良くて、一枚の絵を描くような感じだったんですけど、「空中庭園」からは彫刻みたいに、足りないものは私が見ている世界じゃない、どこか別の世界から持ってきて付けるって感じで、作業が全然違いましたね。

伏線が丁寧に張られ、構成も考え抜かれて印象のある「空中庭園」だが、実はそうではないのだという。

角田:
そもそも、連載の締切を忘れてたんですよ。第一回目の締切が、もう、一ヶ月後ですよって言われて、すごく前に書いた短編を引き延ばして、第一回をしのいだんですね。で、二回目からどうしようという時に、じゃあ、この主人公のお母さんを次に出してみようとか、お父さんを出してみようとかいう風に、苦し紛れにやっていったんです。その一回のことしか考えてないから、次にしわ寄せが全部くるんですよね。つじつまを合わせないとならないから、最後の方は本当に大変で、こんな構成にするんじゃなかったな、と思いながら書いてました(笑)。

この小説をいっそう印象的にしているのが、架空の街の設定だ。ディスカバリーセンターという新しいショッピングセンターがあるばかりの人工的な住宅街というイメージだけは、当初から決まっていたという。

角田:
そういう街にすっごい興味があるんですね。住宅地がばーってあるような街ってすごく人工的ですよね。あそこまで行き届いた人工的なものの中で、何が育まれるんだろうって思うんです。全然、これは否定的な意見じゃなくて、どういう可能性が生まれて、どういう可能性が踏みつぶされていくのかっていろいろ考えちゃうんですよね。それから、休日にみんなが同じところに行くっていう心の動きとかって、自分も住んでたら絶対行くんだけど、興味深いなあって思いますね。

「空中庭園」に限らず、角田さんは小説を書き始める際、まず場所をイメージしてから書きだすのだそうだ。

角田:
舞台が決まらないと、心の持ちようが決まらないっていうのはあると思います。例えば、学校だったら、開放的な学校なのかどうかを考えたりしますね。私はそこの街に海があるかないかっていうのをよく考えています。海って近くに住んでいるだけで、なんか救われると思うんですよね。だから、海があると人は大らかになるし、ないとちょっと閉塞感を感じるのではないかと。それで、海がない県とかよく探すんですよね。この県に生まれた人は日々何を考えているんだろうって。「空中庭園」は、架空の街が舞台ですけど、とりあえず、海がないってことは決めていました。

家族ひとりひとりの視点から綴られているが、最も書いていて面白かったのは若くして結婚した母親の話だという。

角田:
私は主婦じゃないし、それまで自分の視点からしか書いたことがなかったので、最初はすごい不安で、書けないかもとか、嘘くさいかもとか思ってたんです。でも、たったいっこだけでも共感できる気持ちがあったら、そっから入り込んで書けるなと思ったんですね。あのお母さんだったら、とにかく良き者でありたいっていう衝動と、だけどどうやら自分の持ってるものがそんなにいいものでもないって知ってる葛藤みたいなところは私にもあるので。そういう一点だけ分かるとあとはパーっと出来ちゃって、そんなにぶれないと思いますね。

「空中庭園」以後、角田さんはよりストーリーを意識した作品に取り組んでいく。
|
 |
 |
 |




|
 |
第四回
ゼロからひとつの世界を作り上げる作家の仕事。
ゼロが1になる瞬間ともいえる、一文字目を書き付けるその瞬間に至るまで、
プロは何を考え、何をしているのか。
プロの創作の秘密に迫るインタビュー、
今回は『空中庭園』でさらなる新境地を拓いた注目の作家・ 角田光代さんにご登場いただいた。
第四回では、最新作についてうかがうとともに“創作の手がかり”についてうかがう。

|
 |
 |
 『空中庭園』で“私の視点ではないもの”に取り組んだ角田さんだが、現在「別冊文藝春秋」で連載中の「対岸の彼女」でも新たな試みを行っている。
『空中庭園』で“私の視点ではないもの”に取り組んだ角田さんだが、現在「別冊文藝春秋」で連載中の「対岸の彼女」でも新たな試みを行っている。

角田:
簡単に言うと、主婦と女社長という35歳の大人たちの友情の物語というか、そういう違う環境にいる女たちの話を書いているんですが、ものすごく話を作って書いているんですね。ストーリーを作っていきたいと思っているんです。『空中庭園』ってあんまりストーリーはないんですよね。語り手が変わるから何か進行しているように思わせるけど、じゃあ、事件があったかっていったらないし、みんな変わらないままだらだらだらっと行くんで、そうじゃなくて、もうちょっと山あり谷あり、どうなっちゃうの!?みたいなものが書きたいんです。

ストーリーを丁寧に作っていく上で、「ズルをしない」ようにするのが難しいと角田さんは言う。

角田:
例えばふたりを喧嘩させるとしたら、まず、しっかりふたりを仲良くさせとかなきゃならないし、爆発するまでにいらいらをため込まなきゃならないですよね。そういうのが、ストーリーを作ると随所にあるわけですけど、私は実際に書いた方が早いので適当に書けちゃうんですよ。そうすると本当は発火地点に達していないのに、無理矢理、発火地点に行ったようなことが書けちゃうんですね。そこはすごく注意しないと、ウソっぽくなっちゃうので、ズルをしないで、近道をしないようにやってますね。それが私と主人公が一体化してると、簡単なんですよね。いらいらするって気持ちも分かるし、いらいらしてることを無理なく書けるんですよね。だけど、主人公が私とすごく隔たってると、どうしていらいらしているのか考えながらいらいらさせなきゃいけなかったりして、なかなか難しいですね、

さて、デビュー以来、注目作を書き続けてきた角田さんだが、その秘訣はなんなのだろうか。

角田:
怖じけづかない、絶対書けると思うこと。私もよく書くことなんかないんじゃないかと思うんですよね。でも、探せばなにかしらあるんです(笑)。

豊富な旅行経験を持ち、旅についての小説やエッセイも執筆している角田さんだが、これから小説を書こうという人にとって海外旅行という体験は、必ずプラスになるとは限らないのでは、という。


角田:
これは微妙で、あんまり若くして行っちゃいけないと思うんですよね。あんまり若くして行くと書けなくなると思うんですよ。書くって行為よりも旅自体の刺激の方が強いから、書けない。旅で得られる刺激に筆がついていかないんですよね。すっごい面白いことがあったっていうのを日記としては書けるけれど、小説にもってこれない。だから、とりあえず一作は書いてから行った方が絶対いいと思います。すぐに外に出るんではなく、まずは、やっぱり本を読んで、恋愛でもしてみる(笑)。恋愛は大事ですよね。恋愛を一度もしたことがない人ってきっと小説を読めないと思う。

小説を書こうと思った時、まず何から手をつければいいかとたずねると、角田さんはテーマを決めるということをあげた。


角田:
テーマを決めておくとすごく楽なんですよね。今、“他人同士がちょっとした瞬間にすごい親しくなるのだけど、結局それは他人だ”ってテーマで連作を書いてるんですけど、例えばどういう瞬間だったら、自分が見ず知らずの人に心を許せるだろうかっていうのを、なんとなくいつも意識しているんですね。そうすると、実際の生活やテレビなどで、そういう状況に出会ったときには、あ、これだって分かるので、すぐ作品に持っていけますね。

日記をつけている角田さんだが、そういったテーマについてはメモしたりしないのだという。日々の暮らしの中でちょっとした違和感などを感じても、それをいざ書こうとすると忘れてしまったりということが心配な人も多いのではないかと思うのだが。


角田:
でもね、私もよく忘れるんですけど、忘れることってきっと、あんまり大したことじゃないと思うんですよ。だから忘れていいんだと思うんです。覚えてることって絶対覚えてるんで。だから、逆に、これから書く人は、何を自分が覚えているのかっていうのを大事にすれば、きっとすぐに書けるんじゃないかと思います。
|
|
 |
|
 |